コメ価格の高騰が続くなか、小泉進次郎農林水産相は政府備蓄米の放出方法について、異例ともいえる「随意契約方式」への変更を打ち出しました。これにより、価格高騰の抑制を図るとともに、従来の農政のあり方に一石を投じています。
農政の転換とは?
今回の備蓄米放出は、特定業者との直接契約による随意契約方式を採用した点で異例の対応です。従来の競争入札方式では対応しきれなかった市場変動に、柔軟かつ迅速に対処できる新たなモデルになる可能性があります。
さらに小泉農水相は、1970年から続く「減反政策」の見直しにも着手。農家が自由に米作りを行える環境づくりを目指し、持続可能な農業への転換を進めようとしています。
減反政策とは?
減反政策(正式には「生産調整」)は、1970年に始まりました。背景には、戦後の高度成長期に起きた“米余り”による価格下落があり、政府は農家に対して「米を作らない代わりに補助金を支給する」ことで収入を保障する仕組みを整えました。
しかし近年は、日本人の“米離れ”による消費量の減少に加え、補助金への依存が常態化。農業の担い手不足も深刻となり、制度の限界が明らかになっていました。
JAへの不信感が背景に
① 米価の適正への疑念
これまでの競争入札制度では、JA全農など一部の業者が落札を独占的に行っていたとされ、米価が高止まりしやすい構造にありました。こうした状況は、消費者利益を損なっているとの批判もありました。
② 備蓄米放出に消極的だったJA
コメ在庫が過剰であったにもかかわらず、JAは備蓄米の放出に対して積極的とは言えませんでした。このため、価格調整の機能が十分に働いていなかったとみられています。
③ 情報開示の不透明さ
競争入札とは名ばかりで、実際には特定業者しか参加できない仕組みになっていたという疑念もあり、透明性の欠如が問題視されてきました。
今後に期待する変化
今回の措置は、長年続けられてきた農政の“形式的運用”への見直しであり、「時代に合わない制度からの脱却」を象徴する一歩です。
本来、生産者とコメという食文化を守るための制度が、次第に既得権を守るためのものへと変質し、結果として消費者の利益が軽視されていたのかもしれません。
今後の持続可能な米作りのためには、透明性と柔軟性を両立した仕組み作りが欠かせません。若い担い手が希望を持てる農業の実現に向け、小泉農水相の取り組みがどこまで進むのか、注視していきたいと思います。

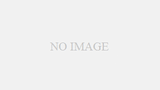
コメント