ジブリ映画『火垂るの墓』をもう一度観直したとき、あなたは清太の行動をどう受け止めるでしょうか?今回の記事では、作者・野坂昭如と監督・高畑勲の視点を手がかりに、作品の奥に潜む“意図”を読み解きます。
作品を語るカギは「視点」にある
本作は、野坂昭如自身の実体験をもとに執筆されました。彼は「妹へのせめての贖罪と鎮魂の思いを込めて書いた」と語っています。つまり、主人公・清太は作者の分身であり、物語は彼の目線で語られています。
反戦映画ではない? 高畑監督が語る本作の意図
一般的には「反戦メッセージ」「残酷なリアリズム」などと評される本作。しかし監督の高畑勲は、次のように語っています。
「単なる反戦映画でも、お涙頂戴の悲劇でもない。戦時下を生きたごく普通の子どもたちの物語だ」
空襲や戦闘シーンが控えめなのも、リアルな“日常の破綻”を描くため。本作の核心は、「悲惨さ」よりも「現実の矛盾」にあります。
清太は“正義の兄”だったのか?
叔母に冷たくされ、妹を守りながら生き抜く清太。その姿は一見美談に思えますが、描写をよく見ると、清太は寝転んで雑誌を読み、オルガンを弾くなど、働きもせず暮らしています。戦時下では「何もしない」ことすら非難の対象でした。
叔母の態度の変化は、単なる“いじめ”ではなく、「誰にも余裕がない」状況下での、やむを得ない“必要差別”とも読み取れます。
節子の死に表れる、清太の複雑な感情
清太は節子を看取り、荼毘に付けるも涙すら流しません。この無表情は心が壊れたからだけではありません。野坂はこう述べています。
「妹のことは、むしろ疎ましく感じていた」
背負いきれなかった後悔と、それが終わったことへの安堵──その矛盾こそが、清太の感情のリアリズムを映し出しているのです。
清太は“普通の青年”だった
野菜を盗み、火事場泥棒もする清太。善悪では語れないその姿に、現代人は戸惑うかもしれません。ですが、それもまた「生きる」という現実の選択肢だったのです。
責めることも、完全に肯定することもできない──そうした矛盾を受け入れることが、この作品の本質だと感じます。
ラストシーンに込められた現代への視線
清太がビル群を見下ろすシーン。その無表情には、きっとこうした感情があるのでしょう。
- 平和への羨望
- 平和への呆れ
もし清太と節子が現代に生まれていれば、餓死することはなかった──そう考えると、あの静かなまなざしが、現代を生きる私たちへの問いかけにも感じられます。
まとめ
『火垂るの墓』は、決して“かわいそうな子ども”を描いただけの作品ではありません。清太の視点から、戦時下での「人としての選択」を描き、そこに込められた“矛盾を抱えた感情”こそが、今もなお見る者の心を揺さぶるのです。

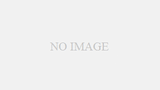
コメント