2025年5月25日現在、依然としてコメの価格高騰が続いています。
そんな中、小泉進次郎農相は、就任直後に政府備蓄米を「随意契約」で販売するという異例の方針を打ち出しました。目標は「5キロ2000円」。
消費者にとっては、連日の高騰ニュースの中で久々に明るい話題だったかもしれません。
でも…現場の農家は困惑。「このままじゃコメ作りは続けられない」
随意契約とは、生産者と購入者が直接価格や数量を取り決める制度です。
一見合理的に見えますが、問題は契約内容が買い手側に有利に設定されがちな点。農家は価格交渉力を持ちにくく、生産コストが上がっても利益を確保できません。
さらに、契約は買い手都合で打ち切り可能なため、農家は次の販売先が見つからず不安定な立場に置かれるのです。
改善には「透明性」と「支援」が不可欠
随意契約が広がる中でも、生産者が不利にならないよう、契約内容の明確化と公正な交渉ルールが求められています。
加えて、行政や関連機関による支援策を強化し、持続可能な農業経営の土台づくりが必要です。
長期的な視点:「価格安定」はもっと構造的な問題
根本には、日本の人口減少とコメの需要減という長期的な課題があります。
今後必要なのは、単なる価格調整ではなく、以下のような「構造改革」です:
- 流通経路の見直しと契約の公平性の確保
- AIによる需給予測や価格コントロールの導入
- コメの価値を再定義し、担い手育成やブランド化を支援
まとめ:消費者と農家、どちらも守る制度設計を
流通コスト削減がメリットとされる随意契約ですが、仲介機能が失われることで生産者の安定利益が揺らぐリスクも見えてきました。
価格の一時的な抑制だけでなく、将来的な人材確保・食の安全保障まで視野に入れた制度づくりが急務です。
私たちの食卓に欠かせない「おコメ」。未来の世代にも受け継いでいけるよう、消費者も少し立ち止まって考えるタイミングかもしれません。

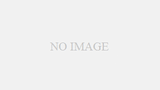
コメント