1. なぜ今、ホスト規制が必要なのか?
2025年5月、ホストクラブを含む悪質な風俗営業を対象とした風営法の改正が成立しました。
風営法は1948年、戦後の治安維持と売春防止のために制定された法律で、キャバレーやパチンコ、ホストクラブなど「風俗営業」に該当する業種を長らく規制してきました。今回の改正は、ホストクラブが抱える構造的な問題、特に未成年や若年女性を中心とした深刻な被害の実態に対応するものです。
2. 実際に起きていた被害の実態
SNSやスカウトから接点を持ち、「売掛」と呼ばれる後払い制度での高額請求に巻き込まれる若年女性が後を絶ちません。恋愛感情を装った依存関係の中で、多額のツケを背負わされ、返済のために風俗業や売春に追い込まれるというケースも報告されています。
- 相談件数の増加:2021年には2,044件だったホストクラブ関連の相談が、2024年には2,776件に増加。
- 個別の被害例:
- ある女性は約2,500万円の借金を抱え、海外での売春を強要されたと証言。
- 大学生の娘を持つ母親は、娘が半年で1,200万円の売掛金を負わされたと訴えています。
- 摘発の現状:2023年1月から2024年6月までに、ホストや性風俗関係者203人が摘発。
恋愛感情を錯覚させたうえでの金銭搾取、暴力的な取り立て、精神的な支配──その実態は「接客」の域を超えた人権侵害です。
3. 注文していない飲食提供の禁止──実効性はあるのか?
今回の法改正のポイントの一つが「客が注文していない飲食の提供の禁止」です。
しかし、現場では「口頭で注文された」「乾杯したから同意とみなす」といった曖昧な主張が通りやすく、証明の難しさが課題です。また、ホストの売上ノルマや煽り文化が根強く残るなか、実質的には抜け道が多く、十分な抑止力になるかは不透明です。
より実効性を持たせるには、監視カメラ映像の保存や、第三者機関による監査制度の導入など、透明性を高める仕組みが必要です。
4. 売掛・立て替えの制度が抱える根本的な問題
本質的な問題は「売掛」という仕組みにあります。客が直接現金を支払うことなく、ホストが「立て替えた」と主張することで、あとから高額な返済義務を負わせるこの制度は、契約書も利率も曖昧で、貸金業としての実態を持ちながらも無法状態に近い存在です。
特に若年層や経済的に弱い立場の人々がターゲットになりやすく、実質的に取り立てや売春への誘導を前提とした金銭回収構造になっている点は見過ごせません。今後は売掛制度自体の是非を、法制度として真正面から議論すべき段階に来ています。
5. まとめ:社会としてどう向き合うか
ホストクラブを含む夜の飲食業には、他では得がたい接客価値があり、それを支持する人も少なくありません。その一方で、曖昧な同意や心理的支配のもとでの金銭搾取が繰り返されてきた事実もあります。
「自由な営業」と「人権の保護」を両立させるためには、透明性ある契約と、過度な依存を防ぐ仕組みが必要です。ナイトワーク全体を否定するのではなく、働く側・利用する側の両方が健全な関係でいられるような“線引き”を、社会として模索していく必要があります。

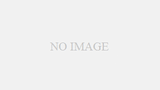
コメント