選択的夫婦別姓の導入をめぐり、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党が提出した法案が、5月30日に衆院法務委員会で審議入りしました。
この法案は、婚姻後も夫婦が別々の姓を選べるようにするもので、旧姓(婚姻前の姓)を通称として使いやすくする仕組みも含まれています。
実は、国会でこのテーマが正式に取り上げられるのは、1997年以来28年ぶり。しかし、今国会での成立には依然として不透明な空気も漂っています。
なぜ今、選択的夫婦別姓が再び議論されているのか?
この制度が求められる背景には、社会の多様化と個人の価値観の変化があります。特に、女性の社会進出が進んだ現代においては、姓の変更による不利益や不便を感じるケースが増えています。
たとえば、結婚を機に名字が変わることで、職場での手続きが煩雑になったり、事実婚を選ぶことで法的保護が受けられなかったりといった現状が指摘されています。
現在の民法では「姓の強制」はないものの、約95%の女性が結婚後に夫の姓を選択しており、事実上の慣習となっています。一方、2020年の調査では、10~20代女性の92.6%が選択的夫婦別姓の導入に賛成という結果も出ています。
1996年に制度が成立しなかった理由
初めて制度が議論された1996年当時は、「子どもの姓はどうするのか」といった不安の声が大きく、特に地方や高齢層を中心に「家族は同じ姓であるべき」という家制度的な価値観が根強く残っていました。
さらに、自民党内の保守派による強い反発や、当時の経済不況など他の政策課題の優先もあって、制度導入は見送られた経緯があります。
28年の時を経て変化した意識
28年前は「必要性を感じない」とする声が多数派でしたが、今では「制度がないことで困っている人」が可視化されるようになっています。
共働き家庭や多様な家族形態が増えるなかで、世論も少しずつ変化。最近の世論調査では6割以上が選択的夫婦別姓に賛成という結果が出ています。
2024年には、超党派による議員連盟も発足し、法制度化への動きが本格化し始めました。
制度導入のメリットとデメリット
メリット
- 個人の尊厳と多様な生き方の尊重:名前を変えずに結婚でき、アイデンティティを保ちやすい。
- キャリアの維持・社会的信用の継続:姓の変更に伴う職場の混乱を避けられる。
- 法的結婚の選択肢を広げる:姓の問題で婚姻を見送っていたカップルにも道が開ける。
デメリット
- 家族の一体感が薄れる懸念:「同じ姓」であることに価値を感じる人もいる。
- 子どもの姓に関する問題:両親が別姓の場合、子どもの姓をどうするかが課題。
- 戸籍制度との整合性:既存の戸籍制度にどのように取り込むかが検討課題。
まとめ:選ぶことの重みと、見守る大人の責任
選択的夫婦別姓の議論は、「家族とは何か」「名前とは何か」「個人を尊重する社会とは何か」といった、深い価値観に向き合う問いでもあります。
「絆」「仲間」「恋人」——それぞれの言葉に感じる距離感や意味は、世代や環境によって違って当然です。
大切なのは、変化に対して軽率に反応せず、きちんと見守り、支える姿勢ではないでしょうか。

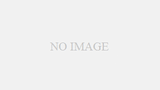
コメント