現在開催中の大阪万博・バルト館にて、来館者を出迎える形で設置されていた公式キャラクター「ミャクミャク」のぬいぐるみが、来場者によって盗まれる事件が起きた。
その一部始終は監視カメラに記録されており、SNSでも話題を呼んでいる。
このカメラが設置された目的は、おそらくぬいぐるみの盗難を想定したものではないだろう。
もし想定していたならば、そもそも手の届く場所に置かれなかったはずである。つまりこの事件は、「想定外」だったはずだ。
では、なぜこんなことが起こったのか?
「モラルの低下」「監視社会への慣れ」「悪気のない軽犯罪」など、さまざまな要因が考えられる。
ただ私が感じたのは、公共の場における“責任感の薄れ”という現代的な傾向だ。
もっとも、「モラルの低下」と一括りにするのも早計だろう。
なぜなら、こうした軽犯罪は決して最近になって突然現れたわけではない。
単に監視カメラの普及によって“目に見える”ようになっただけとも言える。
実際、事件・事故のたびに「えっ、こんなところにもカメラが!?」と驚くこともある。
今では、私たちの日常のほとんどが「見られている」空間にあると言っても過言ではない。
だからといって、「見られているから犯罪をしてはいけない」という理屈は本質ではない。
そう考えると「見ていなければ何をしてもいいのか?」という疑問にすぐ直面してしまう。
現時点では、性善説を信じるしかないように思えるが、少なくとも監視カメラがその“補助線”になっているのは事実だ。
たとえば、カメラ映像による加害者の特定、迷子の保護、事件の早期解決など、防犯カメラの実用的な成果は年々増えている。
また、カメラ設置エリアでは犯罪発生件数が明らかに減少しているというデータもある。
つまり、監視は「安心できる環境づくり」に貢献している面も大きい。
もちろん、プライバシーとのバランスについての議論はこれからも必要だ。
それでも、システムや設備を“敵”と見るのではなく、“使い方”を考える時代に、私たちはすでに入っているのではないか──
今回の事件は、そのことを静かに問いかけているのかもしれない。

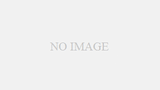
コメント