世界7工場削減の衝撃──追浜と湘南も対象に
2025年5月13日、日産自動車は経営再建に向けた新たな構造改革「Re:Nissan」計画を発表しました。
その中で、2027年度までに国内外で7つの完成車工場を閉鎖し、約2万人の人員を削減する方針が明らかにされ、大きな話題となっています。
国内では、神奈川県の追浜工場と湘南工場が閉鎖の候補として挙げられており、地元を中心に衝撃が広がっています。
なぜ今、国内工場が対象に?
国内2工場が閉鎖候補とされた理由としては、生産効率の低下が挙げられています。
また、アメリカでの関税強化など、外部環境の変化も一因とみられています。
ある社員の方は、
「国内には手を付けないと思っていたので、かなり厳しい」
と語ったそうです。
この言葉からは、予想外の決定に対する戸惑いや不安がにじみ出ているように感じます。
単なるコスト削減ではない
今回の決断は、企業としての生存戦略とも言えるものかもしれません。
事実、日産は前年度に6708億円もの純損失を計上しており、これまでの延長線では立ち行かなくなっていることがうかがえます。
閉鎖の影響を受けるのは社員だけではなく、取引業者や地域経済にまで波及する可能性があります。
とくに、部品会社や物流業者など、工場と密接に関わる中小企業にとっては死活問題となるかもしれません。
モノづくり日本の「今」
日産に限らず、企業がコスト効率を追い求め、海外へ生産拠点を移す動きは以前から見られていました。
それ自体はグローバル経済の流れの中で避けがたい判断とも言えます。
しかし、このような動きが続く中で、「日本国内のモノづくり」が持つ意味も少しずつ変わりつつあるのではないでしょうか。
私の知る限りでは、いまだに昭和時代からの製造設備が稼働している現場もあり、そこでは人の手による細かな調整が不可欠となっています。
かつてはその「繊細さ」こそが日本の強みとされていましたが、自動化技術の進歩により、その価値も相対的に変わってきているように思います。
これからの「技術」と「働き方」
生産現場の変化は、働く側に求められる役割の変化も意味しているのかもしれません。
今後は、手作業の精度だけでなく、高度な管理能力や技術開発力がより重要視される時代になっていく──そんな兆しを今回の工場閉鎖から感じました。
日本という国の中でモノを作り続けるには、それにふさわしい価値や強みを再定義しなければならないのかもしれません。
おわりに:読者のあなたへ
日産の決断をどう受け止めるかは、人によって異なるはずです。
ですが、これは単なる「一企業の動き」ではなく、日本の産業構造の変化を象徴する出来事とも言えるのではないでしょうか。
これからの日本のモノづくりに、私たちは何を期待し、何を支えていけるのか。
そんな問いを、今回のニュースは静かに投げかけているように思いました。

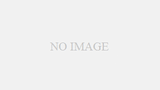
コメント