エル・プサイ・コングルゥ!
『シュタインズ・ゲート』15周年ブログシリーズ第4回!「シュタゲの日」(7月28日)の熱気が冷めやらぬ中、今回は作品の科学的な魅力に迫ります。
タイムリープを支える相対性理論やバタフライ効果を初心者にもわかりやすく解説し、「世界線」という言葉の起源や他作品への影響にも注目。
物理学が苦手でも大丈夫!『シュタゲ』の科学は、物語の感動を倍増させる鍵です。さあ、別の世界線へ飛び込もう!
🔬 タイムリープを支える物理学
『シュタインズ・ゲート』のタイトルは、「運命石(シュタイン)」と「アインシュタイン」を掛け合わせたもの。物語の核心であるタイムリープは、現実の物理学の概念をもとに描かれています。
たとえば、相対性理論は、時間や空間が一定ではなく、速度や重力によって「伸び縮み」することを示します。
『シュタゲ』では、これを応用して、過去にメールを送る「Dメール」や、意識を過去へ移動させる「タイムリープ」が実現。
劇中の「電話レンジ(仮)」は、ブラックホールを模した装置で、データを圧縮し過去へ送信するという設定。
難しい理論を知らなくても、「時間が操作できる!」というワクワク感が伝わります。
もう一つの鍵はバタフライ効果。小さな出来事が未来を大きく変える現象で、たとえば岡部のDメール1通が、紅莉栖やまゆりの運命を大きく左右します。
X(旧Twitter)では「バタフライ効果の描写がリアルすぎる!」との声も多く、科学的な設定が岡部の葛藤や選択の重みを際立たせています。
🌐 「世界線」の起源と『シュタゲ』の功績
『シュタゲ』の象徴的な概念といえば「世界線」。これは、異なる選択や出来事で分岐した並行世界を表す言葉です(例:α世界線、β世界線)。
劇中では、岡部が「世界線変動率」を確認しながら、最善の未来を求めて奮闘。ファンの間では「どの世界線が好き?」と語り合う文化も誕生しました。
この「世界線」という言葉をSF的に広めたのは、『シュタゲ』が最初とも言われています。
2000年頃に話題となった“未来人ジョン・タイター”の話を元に、志倉千代丸が原作に取り入れたとされます。
ちなみに物理学では「世界線」は、粒子の時間・空間の軌跡を指す用語。『シュタゲ』はこれをパラレルワールドの比喩として再定義し、大衆文化に浸透させたのです。
📡 他作品への影響
『シュタゲ』の「世界線」概念は、後のアニメ・ゲームにも大きな影響を与えました。
- 『Re:ゼロから始める異世界生活』の「死に戻り」は、分岐世界の緊張感を彷彿とさせる。
- 『ひぐらしのなく頃に』も、時間の繰り返しと選択の重みに共鳴。
「世界線」という言葉は今やSNSでも一般的で、Xで「#世界線」を検索すれば、『シュタゲ』関連の投稿が多数表示されます。
続編『シュタインズ・ゲート ゼロ』(2015年)では、β世界線を舞台に新たな物語が描かれ、コンシューマーゲーム売上ランキング1位(ファミ通)も獲得。
『シュタゲ』はSFジャンルにおける新たなスタンダードを築いたと言えるでしょう。
📖 科学が深める物語の魅力
『シュタゲ』における科学設定は、単なる演出ではありません。
相対性理論やバタフライ効果が、岡部の選択や仲間との絆に深みを与えています。
たとえば、まゆりを救うためにタイムリープを繰り返す姿は、「運命は変えられるか?」という問いを投げかけます。
ファンの投稿では、
- 「世界線の概念で人生観が変わった」
- 「紅莉栖の理論解説がカッコいい」
といった声も多く、科学が物語のスリルと感情を増幅しているのが分かります。
🚀 次の世界線へ!
「シュタゲの日」の興奮を胸に、今回は科学の視点から『シュタゲ』の魅力を掘り下げました。
次回は、ゲームからアニメへの展開と、ファンの「記憶を消して再プレイしたい!」という熱狂についてご紹介します。
あなたはどの世界線が好き?
Xで「#シュタゲの日」やコメントでぜひ教えてください!
エル・プサイ・コングルゥ!

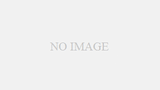
コメント